西南学院は、地球の未来のためにSDGsについて考える機会を設け、
自分たちでできることを行動に移しています。
今号の特集では、西南学院におけるSDGsへの取り組みの一部を紹介します。
西南学院は、地球の未来のためにSDGsについて考える機会を設け、
自分たちでできることを行動に移しています。
今号の特集では、西南学院におけるSDGsへの取り組みの一部を紹介します。
「誰一人取り残さない」未来を目指して
SDGsとは、「誰一人取り残さない」という理念のもと、世界が抱える戦争や飢餓、教育の不平等などの問題をみんなで解決し、末永く暮らしやすい地球を保っていこうという考えです。具体的には2015年に国際連合で採択され、「people(人間)」「prosperity(豊かさ)」「planet(地球)」「peace(平和)」「partnership(パートナーシップ)」の5つのPから始まるカテゴリに分け、2030年までの達成を目指して17の目標が掲げられています。

高校2年生の1年間をかけて、自分たちが興味のある社会課題の解決策を考える探究活動を行いました。この取り組みの目的は、生徒たちが社会課題に興味を持ち、主体的に解決する姿勢を身に付けることです。また、アイデアを表現する能力を養い、他者の発表から学びを得て視野を広げることも目標の一つでした。結果として、多くの生徒が「持続可能な社会」に関心を持ち、中には探究活動を通じて進路を決定した生徒もいたことは大きな成果といえます。生徒たちはこの経験から、社会課題を自分ごととして捉えて真剣に改善策を考えることが持続可能な未来への第一歩になることを実感しました。

高校2年生の頃にクラスメート5人で組んだチーム「地球を守り隊」で「SDGs QUEST みらい甲子園」に挑戦し、2023年度九州北部エリア大会で「アクションアイデア優秀賞」を受賞しました。未就学児から大学院生まで学ぶ西南学院に通ったことで、教育という分野に興味を持ち「教育格差という課題を解決したい」という思いからプロジェクトをスタート。「小学生と大学生をつなげる学びの絆」をテーマに、「L☆earnチケット」というツールを使い、学びたい小学生と教える大学生をマッチングすることで、貧困や人手不足などの課題解決を目指しました。高校の授業と両立しながらのプレゼン準備は大変でしたが、メンバーそれぞれが得意なことを生かしながらデザインや見せ方の工夫を重ねていくことは楽しかったです。今後みんな大学に進学しますが、今回のプロジェクトを経験できたことは良いきっかけになりました。これからもそれぞれの場所や視点からSDGsについて考え、引き続き解決策を実行に移していけたらと考えています。(地球を守り隊)

2024年1月に起きた能登半島地震に対し「自分にも何かできないだろうか」という学生からの声があり、「能登ヘルプ(能登地震キリスト災害支援会)」の支援のもとボランティアセンターが災害ボランティア活動を企画。9月2日〜8日、有志の学生10名と引率職員2名が被災地域での支援活動に取り組みました。具体的には輪島市・珠洲市で被災された個人宅の家財や衣類などの片付けや、損壊したブロック塀の解体・撤去、津波で被災した側溝の土砂かきなどを行いました。被災地での手伝いだけでなく、福岡に戻った後も学生たちがそれぞれに感じたことを周囲に伝えたり、災害復興支援を目的とした学生ボランティア団体「いと」を復活させたりと活動の輪は広がっています。困っている誰かの助けになることが自身の学びにもつながる貴重な機会となりました。
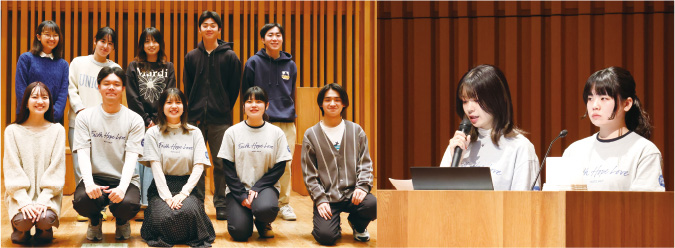

到着直後の印象は、地震から半年以上が経つのに、想像以上に復興が進んでいないということでした。私たちが滞在した数日で進められることはわずかでしたが、『県外から来てくれることが希望だ』と言っていただき、小さくても一歩踏み出すことで誰かの力になれると思えました。また、現地で見聞きしたことを福岡に戻って伝えることの大切さについても強く感じました。大学を卒業した後も自分にできることを見つけ、行動に移していきたいです。(宮田さん)
東日本大震災の時、小学生で何もできず悔しかったことを覚えています。今回は何か力になりたいと、被災地でのボランティアにすぐに志願しました。片付けなど目に見える活動を通じ、被災者の方々の心をサポートする目に見えない支援にもつながると感じました。ボランティアは勇気がいるかもしれませんが、募金することや、支援について調べてみることからでもいいので、他人ごとと思わず、興味を持ってほしいと思います。ボランティア活動を通して良い仲間とも出会え、結果的に自分の成長にもつながります。(井上さん)