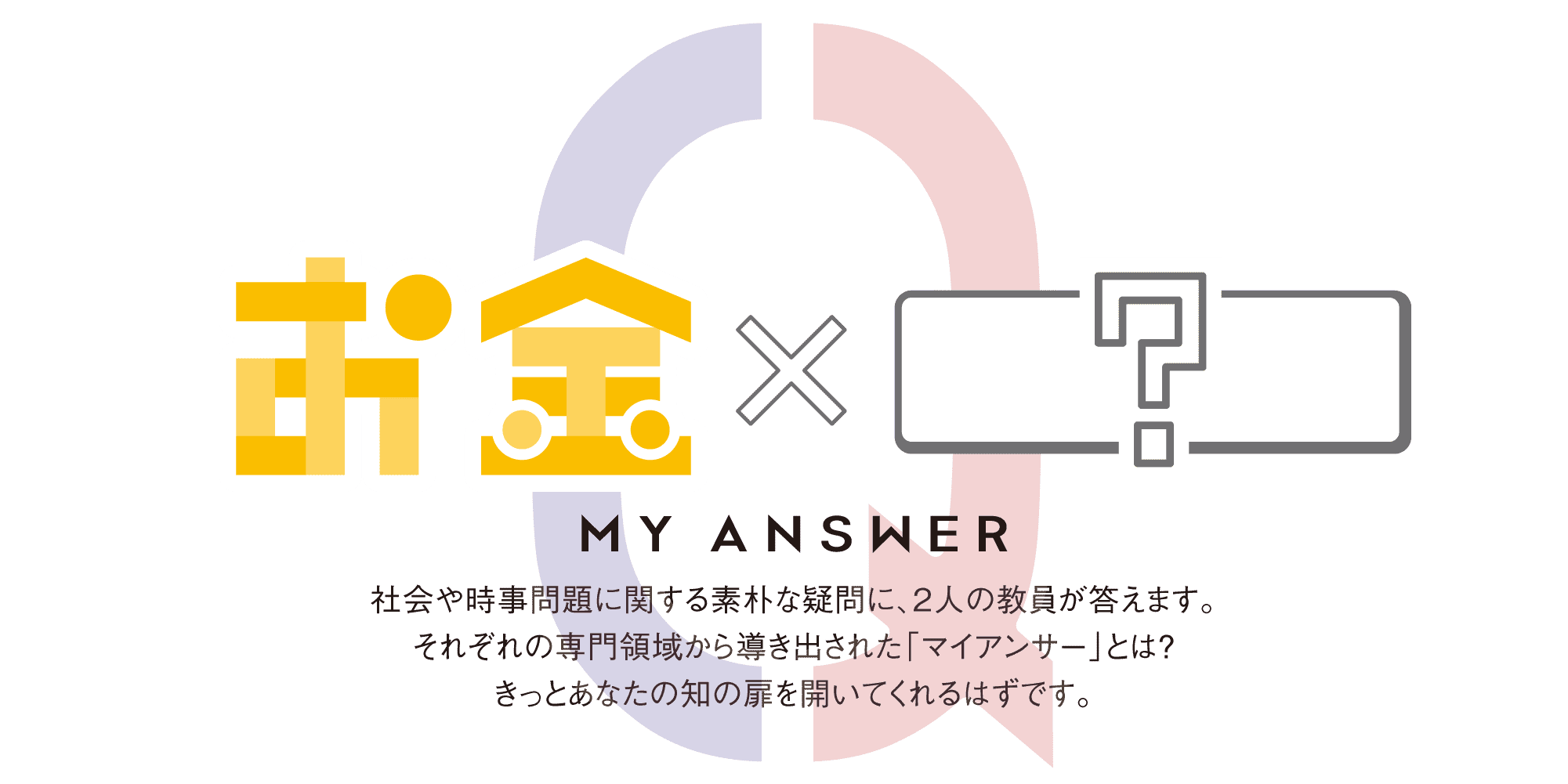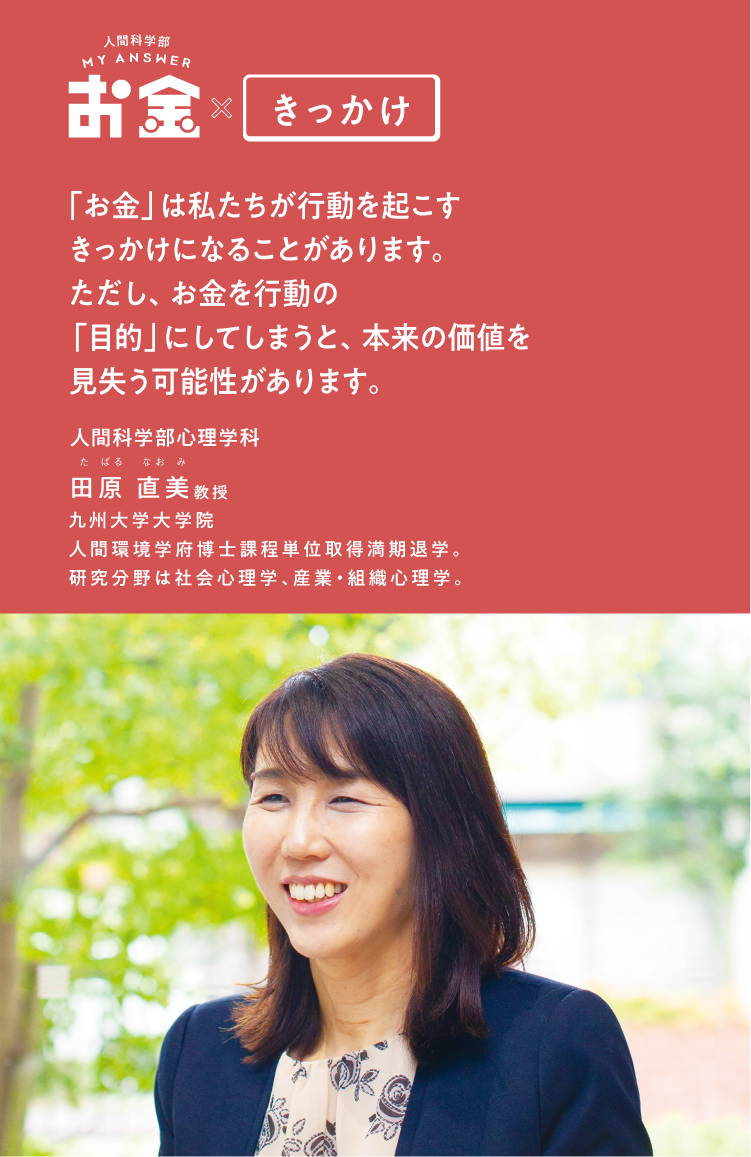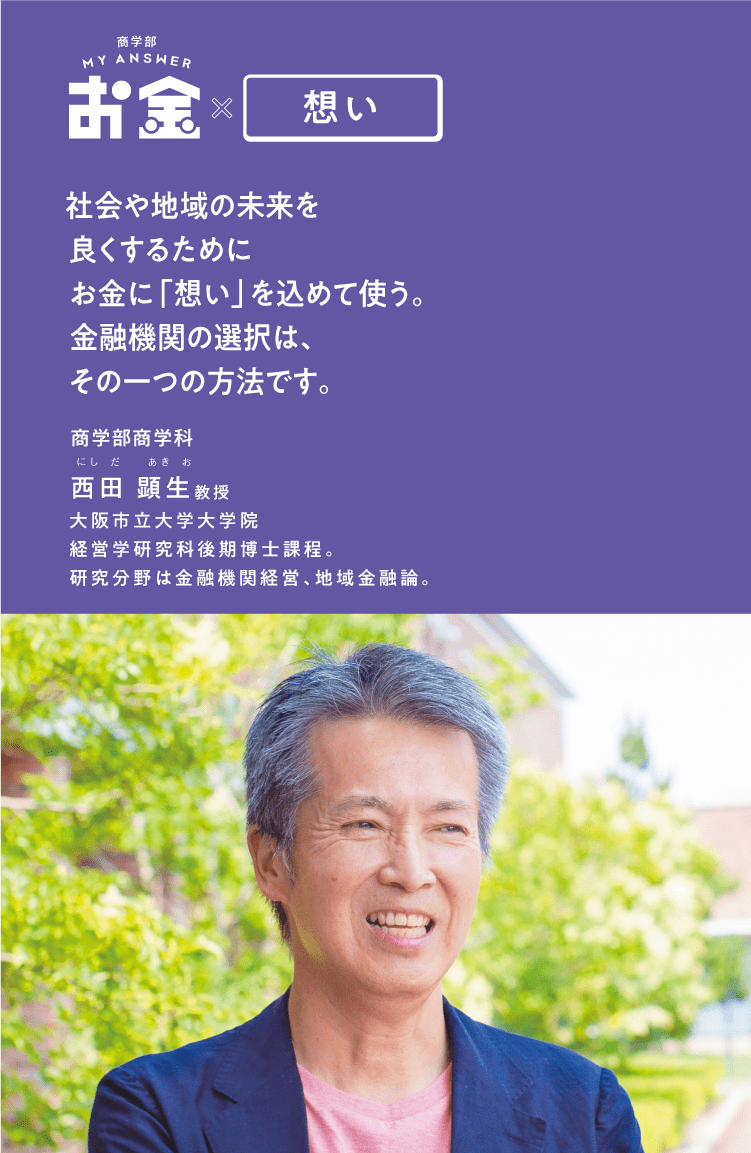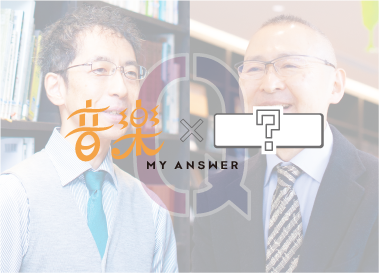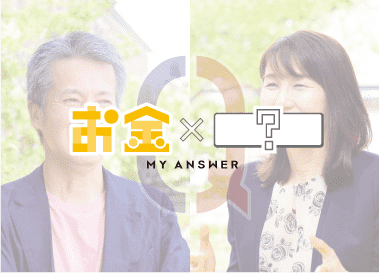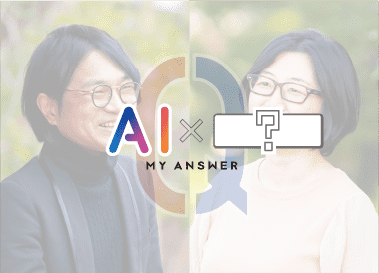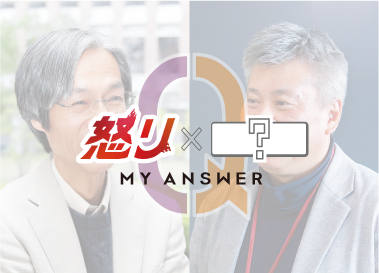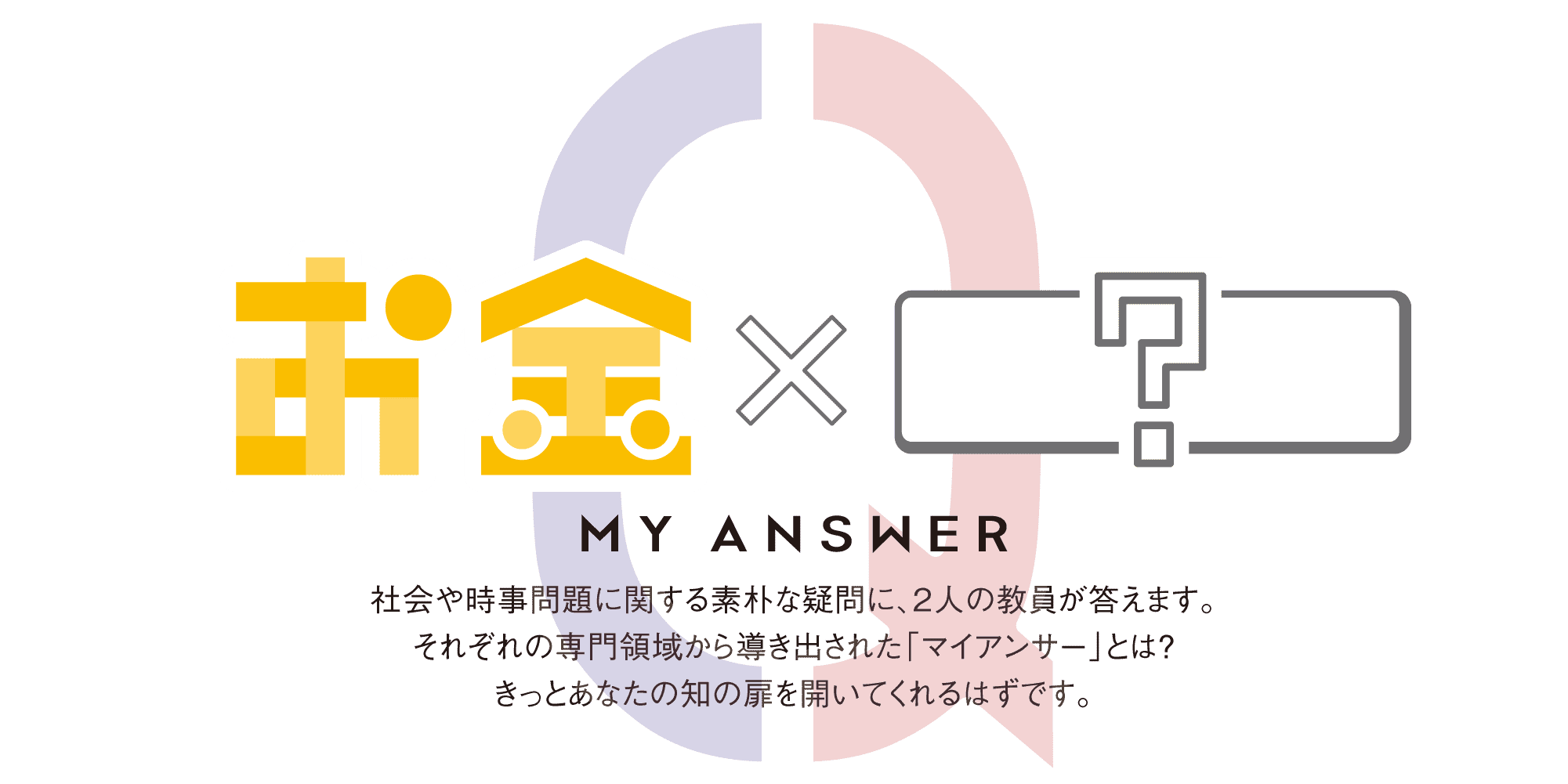
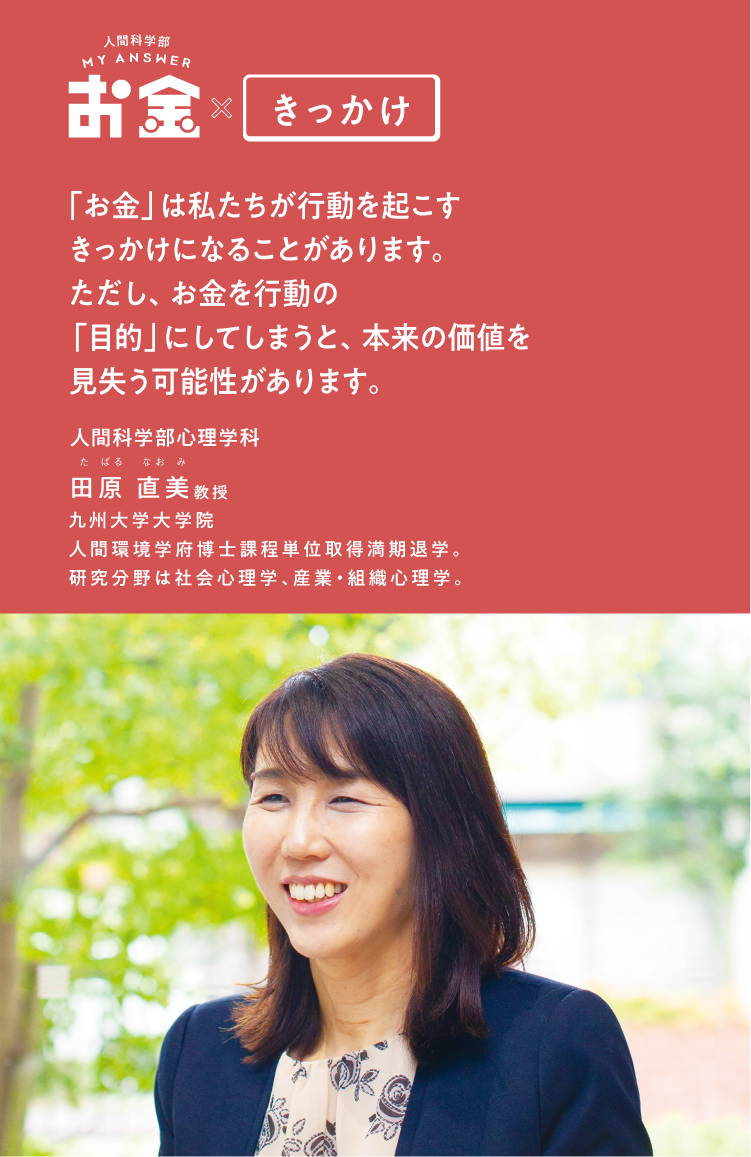
-
お金の額が欲求や幸福感を
満たすとは限らない。
-
「お金」は、人が行動を起こすきっかけになることがあります。例えば、セールやポイントなどによって購買意欲がかき立てられることもあれば、給与や福利厚生が良い企業に魅力を感じることもあります。時には、お金が原因でトラブルや詐欺に巻き込まれるなど、異常事態を招くきっかけになることもあり、良くも悪くも、お金は私たちの行動に影響を与えています。
実際、現金やそれに替わるポイントが物理的報酬として与えられることが、私たちの行動や心理にどのように影響するかについて多くの心理実験が行われています。(※1)
その一つに、「報酬とやる気」の関係を調べる心理学実験があります 。大学生を2つのグループに分け、3日間パズルの課題を解いてもらいました。その過程で、2日目のみ片方のグループにはパズルを解くたびに報酬を与え、もう片方には報酬を与えませんでした。課題終了後の自由時間に自らパズルに取り組む時間を2グループで比較してみると、報酬がなかったグループは3日間を通して時間の増減が見られなかったのに対し、報酬ありのグループは3日目に時間の減少が見られました。つまり、報酬が与えられると、その活動自体に対する自発的な興味関心が失われたのです。その理由は、自分の行動は自分で決めたいという「自律性の欲求」が、報酬によってかえって阻害され、その結果、「楽しみ」として取り組んでいる活動が「楽しみ」という目的から、「報酬」という目的のために行う手段となり、やる気が下がってしまったのです。
また、お金の使い方と幸せに関する実験もあります。(※2)実験のために渡された5ドルを、「自分のため」に使うように指示されたグループと、「他人のため」に使うように指示されたグループでは、後者の方が、幸福感が高まることが分かりました。これは、お金を他者のために使うことによって、相手とのつながりが感じられ、他者と良い関係でありたいという「関係性欲求」が満たされたり、自分が相手の役に立ったと実感でき、有能な人間でありたいという「有能性欲求」が満たされたりするからなのです。
このようにお金の使い方によって、得られる幸福度は異なり、お金は自律性や関係性、有能性という欲求を満たす手段となり得るのです。
※1 Deci,E.L.1975 Intrinsic motivation. New York:Plenum Press.
※2 Dunn,E.W.,Aknin,L.B.,&Norton, M.I.(2008).Spending money on others promotes happiness.
Science ,319,1687-1688.※1 Deci,E.L.1975 Intrinsic motivation. New York:Plenum Press.
-
お金(数値)で測れないことも
大切にしてほしい。
-
お金は、欲求を満たす手段となるほかに、行動の程度や価値を分かりやすく示すための手段(指標)としても用いられます。例えば、仕事の頑張りをボーナスの金額で測ることがあるように、目に見えないものの程度や価値を可視化する手段として「お金=金額」を用いることがあります。
しかし、私たちは「金額」を自律性や関係性、有能性の程度と勘違いしてしまうことがあります。例えば、身の丈に合わない高額な買い物をして有能感が増したと勘違いするようなことです。「金額=自分自身の価値」と思い込むと、お金が目的となってしまいます。
お金は、あくまでも交換可能な「手段」です。お金自体が目的になる、もしくはお金でしか物事の価値が測れなくなると、ギャンブルにのめり込むなどダークな事態を招きかねません。本来の目的を見失わずに、お金と上手に付き合っていきたいものです。
皆さんは学生生活の中で本来の目的を見失ってしまっていることはありませんか。最近はタイパやコスパを重視し過ぎて、効率良くやることが目的になっているように感じます。でも実は、時間や労力がかかることこそ、達成感や幸福感を生み出す力があります。自由な時間に溢れている学生時代こそ、「ただやってみたい」という自分のささやかな気持ちに素直に行動してみてほしいと思っています。それが何のためになるか分からなくても、どっぷり浸かってみる経験が心の糧となり、いつか必ず何かにつながるはずです。
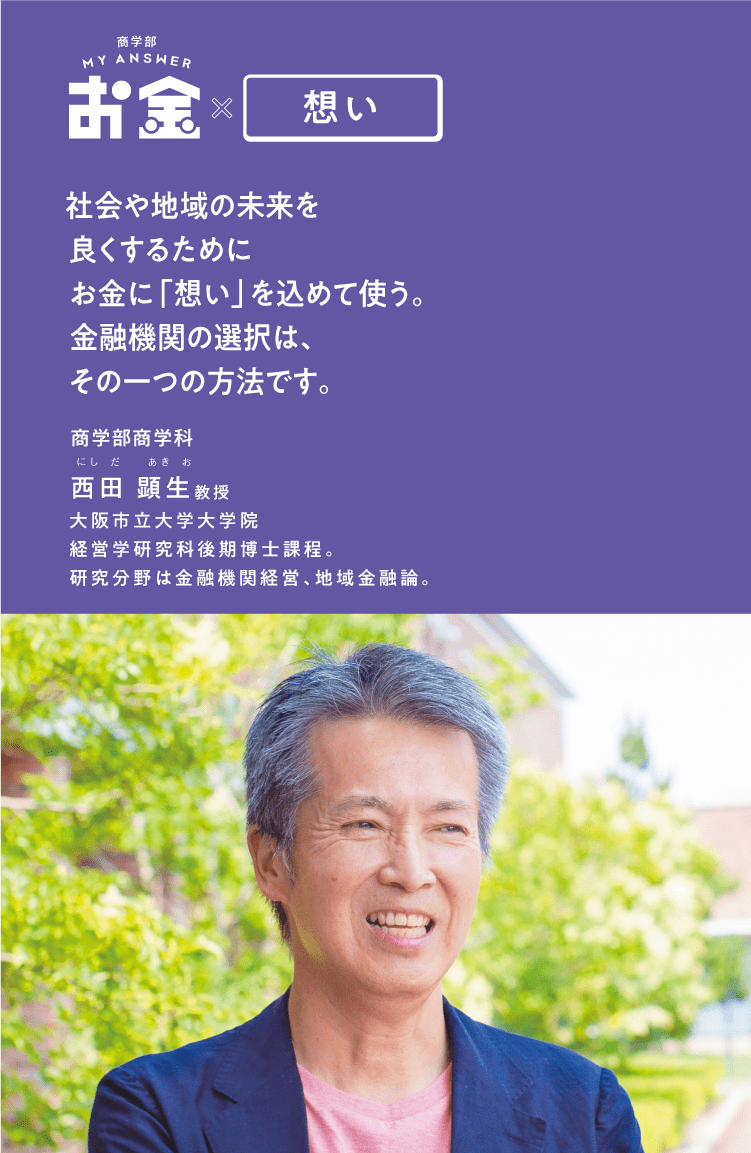
-
複雑化する金融取引の中で、
意図せず違法な行為に加担することも。
-
無機質なイメージがある「お金」ですが、お金に関わる行為の一つである「贈与」の世界では、「想い」を込めてお金を贈ることが当たり前のように行われます。例えば、皆さんも大学合格時にもらった親戚などからのお祝い金には「有意義な学生生活を送ってほしい」という想いが込められています。
では、お金の貸し借りが行われる「金融」の世界ではどうでしょう。「お金は低いところから高いところに流れる」と言われるように、お金は金利が高いところを好みます。お金の貸し借りにおいても、貸し手は高い利子を払ってくれる借り手にお金を貸したがります。しかし、その借り手が世の中にとって望ましい主体、言い換えれば、社会的に真っ当な企業や団体であれば良いのですが、場合によっては環境を破壊したり、武器を製造したりする企業にお金が流れることも。金利の高い海外の投資信託の中にこうした企業の株式などが組み込まれ、結果的に私たちが違法な行為に加担してしまうこともあり得ます。
金融機関が巨大化し、金融取引が複雑化する中、本源的な貸し手から最終的な借り手が見えにくくなっており、こうした危険性は高まっているといえるでしょう。
-
地域の未来を描く
新しいタイプの金融機関が台頭。
-
では、社会の公正と金融の論理を両立するには、どうすれば良いのでしょうか。
一つは、社会的な公正性に配慮した企業やプロジェクトに投資する金融商品を購入し、企業やプロジェクトを応援するという方法があります。最近話題の新NISA制度をはじめ、「貯蓄から投資」を目指す政策も進み、投資信託が私たちにとって身近な金融商品となりました。投資信託の中には、ESG(Environment(環境)・Social(社会)・Governance(企業統治))に配慮した企業やSDGsに積極的な企業に投資する商品も数多くあります。こうした商品を購入することは、ESGに配慮した企業の成長を支援し、世の中を良くすることにつながるでしょう。
二つ目に、社会貢献に積極的な企業やプロジェクトに投融資する金融機関を積極的に利用することで、その金融機関を応援する方法があります。近年では、金銭的な利益よりも、経済社会や環境の持続可能性、地域コミュニティーからの信頼を重視する金融機関が日本でも増えています。
その一例が、信用金庫や信用組合です。株主のために利益を追求する銀行とは異なり、信用金庫や信用組合は地域社会の発展を大きな目的としています。数年前に話題となった東京の第一勧業信用組合は、銀行から融資を受けられない都内の芸者さんを対象に通称「芸妓さんローン」を創設しました。芸者さんを支えることで下町に根付く芸者文化や地域コミュニティーの維持に貢献し、さらには銀行が借り手不足で伸び悩む中、利益を上げています。このように地域の課題を自らのビジネスと結び付け、金融の枠組みの中でお金に「想い」を乗せる取り組みを行い、地域経済と一体となって成長する金融機関が増えています。
ですから、金融機関を選ぶ時、利便性や収益性といった尺度ではなく、「想い」を基準に選んでみませんか。「この金融機関が社会にもたらす価値は何か」「どのような企業や地域を応援しているのか」という基準で金融機関を選ぶようになれば、将来の日本の社会も少し違ったものになるかもしれません。
そのためにも社会課題に興味関心を持ち、自分の価値基準を持ってほしいと思います。そして、自分の価値基準を作るために大学4年間があります。街に出て、いろいろな人と出会い、社会に直に触れてみる。その中で芽生えた「こんな社会になったらいいな」という想いを大学の学びや将来の進路に生かしてほしいと思います。