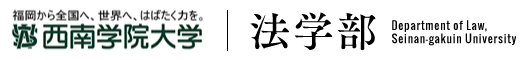2018.09.20
東川浩二氏講演会が開催されました。
2018年9月20日(木)、本学にて金沢大学より東川浩二教授をお招きし、「なぜ外国法を学ぶのか−アメリカ法のススメ」というテーマで講演会が行われました。
本講演会では、東川教授が法学部生に対し、外国法を学ぶことの重要性を語られました。東川教授は学生が外国法を学ぶ理由について2つ挙げられました。1つ目は、日本は比較法大国であるということでした。日本は明治期に仏国のボアソナードらの助けを得て、日本近代法を築き上げました。戦後はマッカーサーの草案を基礎にして、日本国憲法が設けられました。さらに司法改革により、2006年米国に倣ったロースクールの日本での設立が認められ、2009年には諸外国の例を参考にして「裁判員制度」が日本で採用されました。このようなことから、現代の日本で外国法は重要な位置を占めているとお話しされました。2つ目は応用力を身につけることの重要性です。東川先生は、法学分野としてではなく文化研究や教養として外国法を学ぶ必要性について語られました。
次に東川教授は日本の法律家と米国の法律家の求められる能力について説明されました。米国では法的知識だけではなく、「コミュニケーション」や「観察力・推理力・注意力」、「ツッコミ力」を備えなければならないとお話しされました。このうちツッコミ力はお笑いのツッコミではなく、批判的思考力(Critical Thinking)のことだと説明されました。ツッコミ力を発揮すると事実やルール、最終結論も異なってくることを指摘されました。また米国や英国等のコモンローの国ではこのツッコミを繰り返して法が発展したケースがあるとして、いくつかの事例を挙げられました。例えば、「トマトは野菜か果実か」が争われ、ツッコミ力を活かし、「野菜」と認められました。またピザ生地の上にトマトケチャップやその他の野菜が入っているから野菜とされた事例や、スナック菓子として有名な「プリングルス」を大半の国は「ポテトチップス」として扱っているが、英国は材料の中に「小麦粉」が使われているから「ビスケット」として扱っている事例を挙げられました。このようにツッコミ力が影響した事件を熱くお話しされました。
この講演会を通して、国よる考え方の違いを知り、国内法だけでなく外国法を学ぶことの面白さを改めて実感しました。最後に、「外国法を学ぶにあたって一番どの分野を重視しているのか」をお伺いしたところ、東川教授は「言論の自由」が今後重要であると語られました。SNSの普及により、プライバシー関連の事件が浮上してきていると指摘されました。今後は国内法と合わせて外国法の学習を取り入れることで、グローバルな視野で問題と向き合うことができ、将来社会に役立てるのではないかと期待しています。社会人までに更なる知識を身に付けるように努力したいと思います。
記:德田 直紀(法学部法律学科)