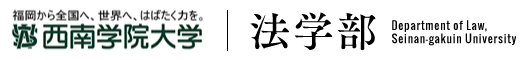2015.04.17
徳田靖之氏の講演会(新入生歓迎講演会)が開催されました。
4月17日(金)、徳田靖之弁護士をお迎えして、「法学部で学ぶ皆さんへ」と題する新入生歓迎講演会が大学チャペルで行われました。
徳田弁護士は、なぜ弁護士になったのかという原点を、生い立ちから大学生活でのエピソードまでを通じてお話してくれました。そして、弁護士になった後、徳田弁護士が成長できたと感じたターニングポイントとなる訴訟と、そこでかかわった人々についてもお話してくれました。共通して強調して話されたことは「出会いを大切に、人とのつながりを大切に。そうすれば、視野が広がり多くのことに気づくことができ、道に外れることなく進むことができる。支えてくれる人も増え、また自分が更に成長できる。」ということです。
徳田弁護士が、お話してくれた数々のエピソードはどれも人や社会、もしも自分だったら、と考えさせられるものばかりでした。中でも印象的で、涙が止まらなかった話を紹介します。
それは、薬害エイズ訴訟です。最年少原告のM君という17歳で亡くなった少年の話を深くお話ししてくれました。訴訟だけでなく差別や偏見、日々迫る死への恐怖、多くの苦しみと辛さの中、強く生き抜いてきたことを詳細にお話してくださり、涙なしには聞けませんでした。
徳田弁護士は、「本来弁護士というものは、正義や社会常識ではのけ者になってしまった被告人や被疑者に対しても、わずかに残っている、もがきながらも本当は真っ当に生きたいという気持ちをひきだして、汲み取り、最後の付添人であるべきではないか。薬害エイズ訴訟を通しては、被害救済ではなく被害回復が重要で、当事者が主人公であるような裁判でなければいけない。「助けてあげる」というのは、上から目線で無意識のうちに差別をしてしまっている、それは間違っているのではないか」と強くおっしゃっていました。
わが身に振り返って考えると、「人として」どうなのか、無意識に差別をしてしまっていないか、と何度も考えさせられました。社会に流されることなく一人ひとりに向ける見る目が変わった、良いきっかけとなりました。また、法律を学ぶ上で考えさせられたことは、同じ法律であっても、立場が変われば武器にも盾にもなるし、はたまた、すべての法律が正しいわけではないということです。それは私たち国民として厳しくチェックしていく必要があります。そういう目を養うことができるのは、日々の授業で触れる幅広い判例や、先生が話題のニュースを取り入れて話してくれる生の授業があってこそです。ただ社会に流されるのではなく、せっかく法律を学べるのだから、昔の人たちが積み上げてきたものと出会うことも大切だと思いました。過去、現在、未来で出会う人たちを大切にして、どうやってよく生きるかを、常に考えていこうと思います。
(記:橋本歩実(法学部法律学科 4年))