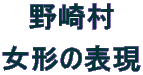
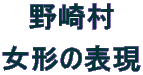

<はじめに>
私がこのテーマを選んだ理由は、男が男役でまたは女が女役で演技するというのは映画やテレビドラマ、その他演劇では当たり前のようなことになっていますが、歌舞伎の女形のように男が女役を演じ、またその「男が演じている女」がさらに何かの役になって演技をするという方法が新鮮だと感じたからです。
―女形役者、坂東玉三郎さんの考え―
○女形とは→男女という命題を乗り越えた一つの作品。
女形を音楽や絵画でたとえると、
肉体=楽譜を書き込む台紙、絵の具をのせるキャンバス。
毎日の稽古=自分の頭に浮かんだ想念を的確に表すための技術に対する研鑽。
○役者にとって「形」とは→言葉のようなもので心の表れ。
人間が生まれた時には何の情報もなく、自分の形はいっさい持っていない。少しずつ自分の環境に根付くための情報に触れ、学習を繰り返し、自分を表現するための形を身に付けていく。
形には決まりがあり、形を間違えれば心を伝えることはできない。例)あ・い・う・え・お、にも口の形があり、言葉を間違えたら言いたいことは伝わらない。
幼いころから形を習得したほうがいいというのは、母国語を会得するように形を身に付けることによって初めて、作為から逃れることができるから。
痛いと思った瞬間に、口が「い」の音を形作っているか、あるいは「あぅ」になっているかというのを役者は体得するために苦心する。
○女形は仕切りという意味での決まりが二重構造になっている。
1.男の部分と女を表現する部分の仕切り→自分の肉体と女の肉体がどう違うかと考える。
2.着物を着ているのか洋服を着ているのか。最終的にはその人間が地球のどこにいるのか。
風のようなもの(湿気、温度、におい、味、光など)が自分の仕切りになっている場合は、それを他者に伝えるのは肉体と感覚の関係であり、感覚だけでは伝えられないところに形が必要となる。
<「野崎村」の中の女形>
「野崎村」の作品では、お染とお光という、ともに久松を慕う同じ年ごろの若い二人の女性が、育った環境や性格によって対照的に演出されている。
―あらすじ―
野崎村の百姓久作の養子である久松は油屋という質屋で奉公をしていて、そこの娘お染と恋仲になる。ある日久松は預かった金を紛失してしまい、久作がその金を立て替え一旦この場は収まるが、久松は野崎村の実家に戻される。
そこで久作はこれを機会に、盲目で余命短い妻お幸の兼ねてからの願いであったお光と久松の祝言をあげさせようとする。お光は想いをよせていた久松と祝言をあげることが決まり、心を弾ませる。久松もお染との身分の違いがある恋をあきらめ、お光と一緒になろうと決意する。
そこへお染が野崎村に久松に会いに来る。お光はお染の姿をみるなり嫉妬して追い返そうとする。久松はお染に親が薦める縁談先の山家屋へ嫁に行くようにと諭すがお染は久松と一緒になれないならば自害すると言いだし、とうとう久松もお染と一緒に死のうと決意する。
すると久作が、以前自分が立て替えたお金は、なけなしの田畑や衣類、お光の髪飾り等を売ってこしらえた金であったことを明かして二人に意見したところ、二人は何も言えなくなり別れることにする。
喜んだ久作は早速久松をお光と祝言させようとお光を呼んだ。するとお染と久松が死ぬ決意だと悟っていたお光は自分が身を引こうと思い、髪を切って尼になっていた。久作はお光に自分の思い至らなさを詫びた。
そこへお染の母お常が姿を見せ、先に久作が出した金は改めてお光への布施物として返され、お常は久松が店に戻ることを許し、けじめをつけるためにと自分とお染は船で、久松は駕籠に乗って大阪へ帰っていった。
―対照的な二人の女形―
|
|
お染 |
お光 |
|
育った環境 |
商家の娘。都会。 |
百姓の娘。田舎。 |
|
性格 |
外交的で情熱的なお嬢様。 |
内向的。きつい性格。 |
|
衣装 |
派手な模様の大振袖、だらりの帯、きらびやかな髪飾り。 |
納戸色の地味な衣装にすすきのかんざし。きりっとしたメイク。 |
○お染の演技表現
○お光の演技表現
お染以上に至難な役。紙で眉毛をかくしてみたり、膾をきざんだりする件の浮きたつような気分とはじらい、お染への嫉妬、尼になってからの愁いなど。
<まとめ>
歌舞伎は肉体の魅力を表現するというよりも、演じる役によって決まっている鬘や衣装、メイク、動きという決まった形に自分自身が入り込み、表現する演劇だと思いました。そして毎日の稽古によってその動きが自然にできるようにするために肉体を鍛え上げていくのだと思いました。
歌舞伎での肉体の使い方をバレエと比較すると、バレエではきちんと踊れるように訓練した肉体は、その肉体そのものが視覚的にも美しい芸術になります。
しかし歌舞伎では心を表現するために稽古でしっかりと形を身につけ鍛えた肉体は、その肉体そのものが芸術とはならず、その肉体の担う役割は表には見えないけれども、頭から足先まで身体全体をすっぽり覆っている衣装の下でしっかりと形が身についた道具としてその演技の表現を支えているのだと思いました。
女形の役者が、男の身体で女を演じることができるのも、その道具としての肉体に女の形をしみこませ、役として自由に駆使できるまでに完成させているからだと思います。
和角仁著『歌舞伎入門』(文研出版,1976)
ビデオ 歌舞伎鑑賞入門 5 世話物 「新版歌祭文」を中心に(NHK,1992)
坂東玉三郎ホームページhttp://www.tamasaburo.co.jp/
野崎村 両花道の作る空間http://www5e.biglobe.ne.jp/~freddy/watching101.htm
新版歌祭文http://www.geocities.jp/gaulare/contents/love/osome.html
![]() 演習2006
演習2006