

私たちは通常感情を持って生活をしている。〈楽しい、嬉しい、悲しい、切ない〉などと感じながら日々を過ごしている。また私たちはさまざまな動作をすることが可能だ。〈歩く、何かを持つ、笑う〉といった動作を何気なく行っている。つまり私たちは日常、当然のごとく「心と体」を所有して生きていると思い込んでいる。だが私たちは、〈心〉を見たことがあるだろうか。もし私たち人間に〈心〉が存在しないとしたら、私たちの〈体〉とは一体何と捉えられるだろうか。このとき私たちの〈体〉は、機械やロボットと同じではないのかという不安や疑念が生まれてくる。だがどう意識しなおしてみても、私たちは自分のことを機械やロボットと同じ存在だとは認識できないものである。そこで私は、「人間の肉体は、機械やロボットとは異なる存在である」ということを仮説として立てることにする。この点を映画『etoiles〜les danseurs de l’Opera de
Paris〜』等を通じて証明していく。
映画『etoiles〜』には、パリのオペラ座バレエ学校に8歳で入学したものたちが、エトワールと呼ばれる学校中のトップバレリーナになることを目指し、遊ぶ時間も持てない状況の中、厳しい練習を行い、競い合っていく様子がドキュメンタリー風に映し出されている。しかし、彼らは厳しい規律を保ちながら、肉体を鍛え続け、舞台に出るまでは常に緊張と不安に駆られる状況を、自分の人生を犠牲にしているとは決して考えない。生徒の一人は映画の中で『バレエを続けることで人生を犠牲にしているなんて思っていない。ただ努力をしているだけであってそれは至福なことなのだ。』というようなことを語る。私はここで、自分の肉体を鍛え自分の可能性を拡大し続けることによって自分を脱し続ける行為に喜びを覚えるのは人間の特徴ではないかと思った。機械やロボットが各々の可能性を拡大し続けることはできないし、ましてやそれによって喜びを得ることは当然不可能だ。さて、ここで新たなことに着目してほしい。先ほど述べた、自分を脱するという時の「自分」とは一体何をさすのか、ということだ。母親の胎内から生まれたときの自分、バレエで肉体を鍛え始める前の自分…一体いつの「自分」だというのだろうか。私たちは、自分を自分として捉える時に、自分以外の何かを通してしか自分を捉えることはできないのだ。だから、この映画でバレリーナたちが自分を脱するのを捉えるのに「鏡」を用いていたのだ。「鏡」の前で肉体を鍛えることによって、自分を脱することも可能になり、そこから喜びも生まれるのだ。
バレエの見所といえば、今まで述べてきた肉体を鍛えていき、肉体にテクニックを得させることで人間の肉体の限界を広げていくことの感動にあるのだが、肉体の限界が広がれば広がるほどその人間は、人間として「疑わしい存在」になっていく。なぜなら、テクニックをさまざま身につけた人間は、このボタンを押せばこう動くと決まっているようなまるで機械やロボットのような存在のように見えるからだ。しかし、「人間の肉体は、機械やロボットとは異なる存在である」のだ。ここで、人間の肉体と機械やロボットとの違いを比較していく。機械やロボットが動くとき、主に私たち人間が操作主となり、機械やロボットが操作されるという関係が存在する。そして、操作主と被操作主の関係は支配関係にある。当然この二者は別々の存在だ。しかし、人間の肉体の場合は異なる。肉体を操作する別の存在は存在せず、もちろん支配関係などもない。肉体を操作するものがあるとすればそれは精神ではないだろうか。ここから、人間の肉体は、機械やロボットとは異なる存在であるといえる。機械やロボットが動くには、操作主という他者が必要であるが、人間の肉体を動かすのに他者は必要ないのだ。人間の肉体を動かすのはその人間の精神であり、そこには支配関係はなく、人間の肉体と精神は一体化しているのだ。
バレエを通じて、私が挙げた仮説は証明されたことになるが、このことは私たちの日常において考えてみても当てはまるといえる。私たちは自分自身でもきづかぬうちにこっそりと日々バレエを踊っているのだ。自分を鍛えることにより、自分の可能性を広げ、それを何かにぶつけて確認し、喜んでいるのだ。実際に体を動かすといったことだけではなく、日々誰かと会話をすることだって私はバレエ的な要素を含んでいると思うのだ。なぜなら、私たちは生まれた時は言葉を使って自分の考えや気持ちを表現することはできない。しかし、生活をしていく中で言葉を話すというテクニックを身に付けていく。そうやって言葉で考えや気持ちを表現できているかを確認する時には、他者という鏡の存在が必要になる。そして、他者という鏡によって自分の考えや気持ちが伝わったと認識できた時、私たちは喜びを得ることができると私は考えるからだ。
私がこのゼミで一番学んだと思うことは、芸術作品を自分の日常の視点と同じ高さで観察することの大切さだ。ステージの上のものとして、自分の日常と切り離して見たとしても、芸術作品に心を動かされることはあるのだが、「もしかしたら自分の日常となんら変わりはないことを表現しているのではないだろうか」という視点をもちながら観察していると、より肉迫したものとして作品を捉えられると思ったのだ。
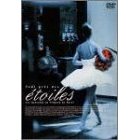 |
【参考】
・ 映画『etoiles〜les
danseurs de l’Opera de Paris〜』(2002年)
・ 『フランス現代思想を読む』 渡辺諒 /白水社
・ 『20世紀フランス思想を読む』渡辺諒 /白水社
・ 『ミシェル・フーコー』 サラ・ミルズ 酒井隆史訳 /青土社
![]() 演習2006
演習2006