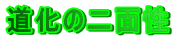
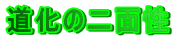

あなたは、ピエロと聞いてどんなイメージを思い浮かべるだろうか?
愉快?楽しい?滑稽?寂しい?悲しい?
それとも、恐怖、だろうか?
私の周りにピエロを心底怖がる人がおり、その人に出会うまでピエロを恐怖だと感じる人がこの世にいるなんて考えたこともなかった。たとえ、スティーブン・キングの『IT』を見たことがあったとしても。しかし、意外にもピエロを恐怖だと感じる人はかなり多く存在している。
なぜ、人を笑わせるはずのピエロが、怖がられるのだろうか。
この二面性はどこから生まれたか。
そこで、目をつけたのは道化だ。
あなたの道化のイメージは何だろうか?
私は、道化とピエロはイコールではないと考える。しかしピエロは道化だと言う事が出来るだろう。つまりピエロは道化の中のひとつだからだ。
道化というのは、人に笑われる様に演じなければならない。それが定義だ。
人は生きる限り、多くの困難にぶつかる。時には、悲しみにふけったり、悩み苦しんだり。しかし、実はちょっと見方を変えると滑稽だと思えるのはよくある事だ。それを演じて笑わせる、それが
道化である。
道化はもともとイタリアのコメディア・デラルテから生まれ、各地を回り、その土地にちなんだ事件や出来事を織り交ぜながら、即興で劇をし、お客さんを笑わせていた。その人気はイタリアだけではなく、ヨーロッパ各地に広がっていった。
そうしたコメディア・デラルテのように地方を回る道化もいれば、宮廷にかかえられた道化もいる。彼らは宮廷愚者と言われ、古くから西欧において、身体に障害を持った個性ある者を宮廷に置いていたのだ。彼らを抱えることが美徳につながるという習慣もあり、また、彼らは占いや魔よけとしての役割もあった。そういった、宮廷愚者の中にも、パロディー、物まね、即興の才を持つ者もいた。当時の王侯貴族たちは、自分の愚者の賞賛を自分自身への賞賛と受け取り、彼らは誇りだったのである。こういった愚者は、ベラスケスのラス・メニーナスにも描かれている。
またこの頃の道化師は、機知にとんだ言葉や面白い悪戯をすることで愉快なものとして愛されてきた。色々なものが存在したが、後に残ったのは、鋭い風刺の才を持った、騒々しく挑発的な道化役者であり、おどけた行動や仕草、粗雑ふざけが大衆受けする道化の特質となったのだ。道化は風刺とおどけさえ上手く演じる事が出来れば経済的に自立できるのである。
しかし、それが上手くなる為には、やはり機知に飛んでいなければならない。そして、何よりも観察力が必要ではないか。事件や人の悩みを取り上げるのだから、まず人の苦しみや悲しみを見なければならない。しまいには、それをネタに人を笑わせないといけないのである。常にそういうものに目を向けていなければならない。彼らは、人の悩みや真実を映す『鏡』なのである。宮廷愚者は、宮廷を映す鏡、街の大道芸人は、町の人々を映す鏡なのである。鏡というものは、大体あやふやな物で、「鏡のようにありのままに」と「鏡のようにおぼろげに」といったような、まったく正反対の二面性を持つものである。そう、道化も同じである。街の中でも、宮廷の中でも、彼らは、常に色んな人を観察し、時に彼らは人の裏の姿を見ることもあっただろう。彼らは時に真実も知っていたのである。宮廷道化は、閉鎖した宮廷という空間の中で楽しませる役割があるが、その他にその場を引っ掻き回す役割がある。人間は主従関係の中では間違っていたとしても、間違った方向、主の意見に流されやすい傾向がある。そこで道化が口をはさむ事でその場の空気を変え、引っ掻き回し、凝り固まった意見を解す。道化はあくまでもおどけた振りをして、全体が間違った方向へ進むのを防ぐのである。
鏡イコール道化。私たちは、自分の姿を鏡を通してでしか、見る事が出来ない。自分の目で自分の顔や後ろ姿、全身を見ることは出来ない。そして、鏡の役割の道化は、演じることで、普通の鏡では見ることの出来ない、人間の内面を自分に滲み出させ、映し出すのである。そうして私たちは気付くのである。悩みというのは、時に滑稽だと。そして、あれは自分かもしれないと。そして、その事がしめす可能性は、人はそれをみて笑うのであるが、実は笑われているのは、道化ではなく、私たち自身なのかも知れないということだ。それに加え、派手な化粧で顔をすっかり隠し、何を考えているのか分からないピエロ、そんなところにも、人は恐怖を抱くのかもしれない。
道化の二面性。それは何処から生まれてきたのか。
しかし、それはどこからも生まれてないのである。なぜなら、初めからそこにあったのだ。人は演じた時、そこにすでに二面性は存在している。私たち人間は、なりたい自分になる為に、常に演じている生き物だ。道化だけに二面性があるのではなく、私たち全員に二面性があるのである。
おどけた表現をしながらも、私たちに伝えているものは、真実なのだろう。
人間は皆演じていると。
![]() 演習2006
演習2006