シャンゼリゼと凱旋門
〜perspectiveの視線〜

パリで最も華やかな通り、シャンゼリゼ。このシャンゼリゼ通りは、エトワール凱旋門から放射する12本の通りの一つである。現在、このシャンゼリゼ通りを、観光客がたくさん訪れている。私もいつか訪れてみたい。そこで、ここを訪れたら、是非見てみたいものがある。そのエトワール凱旋門から、西と東を眺めてみる。そうすると、東には、シャンゼリゼ大通りからコンコルド広場を通って、テュイルリー庭園、さらにルーブルに至る眺望が開けている。そして、西を眺めると、グランド・アルシュ(新凱旋門)が一直線上に見えるだろう。きっと、ここからの眺めは、開放感にあふれて、絶景だろう。
このエトワール凱旋門を中心とした、まっすぐな直線は、「パリの偉大なる軸」などと呼ばれているらしい。まさにこのスポットは、パリの中心として存在しているのではないかと思う。
この直線上の建築物は、古いものは12世紀、新しいものは、20世紀のものである。しかし、12世紀の建築物と、20世紀の建築物という、800年という年月の隔たりを持つ建築物が一つの視線の中に入っていても、違和感を覚えないと思う。古いものと、新しいものがうまく融合した都市だと感じた。
では、ここで、perspectiveの「視線」が生まれた経緯を見てみよう。
エトワール凱旋門から東西に、8キロ近い直線が引き終えられたのは、18世紀、ルイ15世の時代であった。それから、歴代の造営者達は、その整備、新設に力を入れてきた。この直線のきっかけは、12世紀のルーブル宮の建設であった。なぜ、ルーブル宮から、直線が引かれようとしたのか。私は、なんとなくヴェルサイユ宮殿の作りと何らかのつながりを感じた。ヴェルサイユ宮殿は、宮殿の正面から、まっすぐに庭園が伸びている。写真で見ると、やはり、perspectiveな効果を持つ作りになっていた。ここで共通しているのは、宮殿から、王が庭を眺めたとき、宮殿より高い建物がなく、また、ざっと一瞥した時、宮殿の目前の状況がすぐにわかるようにまっすぐに伸びた「視線」を持つことは王にとって必要なことだったのではないかと私は思った。
ルイ14世は絶対王政の小世界をヴェルサイユに作り上げた。それは、「視線の政治」と呼ばれていた。視線によって、宮廷内の社会的制御を行う儀礼の規律の世界だった。王の視線が宮殿の中央からまっすぐに限りなく伸びることは、絶対王政時代の美学とされていた。庭園も当然王の「絶対視線」に服従せざるを得ない。視線上に王に対立するものがあってはならない。これによって、「直線の美学」が生まれたのではないのだろうか。
この「直線の美学」を持って、または、王の絶対的な「視線」というものをルーブル宮、テュイルリー宮殿でも、作り上げようとして、宮殿からの視線の軸、つまり、ここではシャンゼリゼを限りなく伸ばすことで、直線の美を表そうとしたのであろう。
テュイルリーやヴェルサイユのように、建物の正面から軸線をデザインすることが、常套的な手段となり、パリに軸線を伴う記念建造物が建てられてゆく。軸線の逆方向から見れば、建物は王の視線を受け止めるものとなってゆく。軸が主役となり、建物や記念建造物がそれに付随する、「逆転した絶対軸」は、19世紀のパリを改造したオスマンも多用し、現代まで都市計画の典型的技法として生き残ったのである。
さて、では、軸に付随するように建てられた建物、記念建造物を見てみよう。
1804年、ナポレオン・ボナパルトが皇帝になった。彼は、ルーブル、テュイルリーをフランス施政者の本拠として世界に栄えのあるものにしようとした。1806年5月、イタリアでのオーストリア軍に対する戦勝を祝うためカルーゼル広場に凱旋門を作らせる命令を出した。そして、1808年に完成した。
また、ナポレオンは、オステルリッツの戦いの勝利の後、巨大な古代ローマ風凱旋門の建築を思い立つ。建築家シャルグランが設計を担当し、1806年から、エトワール広場で工事が始まったが、ナポレオンの没落によって、工事は中断されていた。30年後の1836年に完成したのが、エトワール凱旋門である。
ルイ15世が作ったコンコルド広場の整備は、J.I.イトルフという建築家にゆだねられた。イトルフは、エジプトから寄与された、ルクソールのオベリスクをコンコルドに持ってくるため努力をした。コンコルド広場の整備が終わったのは、1836年だった。
また、このイトルフは、凱旋門の周りの整備も担当した。彼は、直径120メートルの広場から12本の道路を放射させた。道路で挟まれる敷地には、同じ形の建物を並べるように義務づけた。この形態規制は今でも続いている。
エトワール凱旋門から、シャンゼリゼ方向への視線の最後を受け止めていたテュイルリー宮殿が、1871年のパリ・コミューンで焼き討ちに会い、この軸の視線の最後を受け止めていた建築物の代わりにその役目を担うことになった、カルーゼルの凱旋門は小さすぎたので、「パリの偉大なる軸」を終結させるために新しく建築物をそこに建てようとしていた。
それに対処したのが、ミッテラン大統領だった。彼は、革命200年記念の1989年、ルーブルにガラスのピラミッドを作った。これが、エトワール凱旋門からシャンゼリゼ方向を見たときに、軸の視線の最後を受け止めている建築物となっているそうだ。これによって、ルーブル宮が作られ、800年以上がたったころ、近世以降のどの為政者もこの軸にこだわり、その形成に寄与し、「王侯事業」として継承してきた、エトワール凱旋門から東へのまっすぐな軸が終結したことになる。
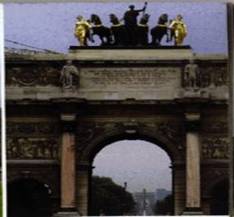
(左)カルーゼルの凱旋門
凱旋門の間から、コンコルド広場のオベリスク、また、その先に、エトワール凱旋門が見えている。
(左下)凱旋門の上から西への眺め
グランド・アルシュが一直線上に見える。
では、次に、エトワール凱旋門から西への軸はどうなったかというと、1900年代に入って、パリ市とセーヌ県がエトワール広場から、デファンスまでの整備計画を立てる。デファンスには、超高層事務所が並び、外周に高層住宅が配置される。象徴的な軸上に出現した、業務地区の中心にフランス革命200年記念の際、グランド・アルシュができた。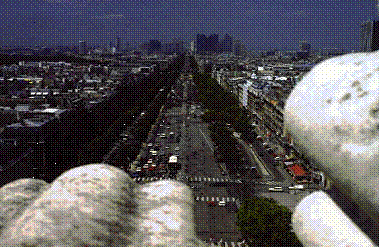 エトワール凱旋門から西を見た際の、軸の最後を受け止める建物なので、これの構想には、そうとう時間をかけたようだ。ミッテランによって選ばれた、このグランド・アルシュは、ルーブル方形宮の中庭の一辺の長さである、100メートルを一辺とする、平方体で門形になっている。また外見は凱旋門の形をしており、しかし、中身は事務所である。ルーブル宮と、凱旋門をうまくミックスさせ、かつ、現代的な、このグランド・アルシュの完成によって、このエトワール凱旋門からまっすぐのびる軸の両端は、ようやく完結したのであった。
エトワール凱旋門から西を見た際の、軸の最後を受け止める建物なので、これの構想には、そうとう時間をかけたようだ。ミッテランによって選ばれた、このグランド・アルシュは、ルーブル方形宮の中庭の一辺の長さである、100メートルを一辺とする、平方体で門形になっている。また外見は凱旋門の形をしており、しかし、中身は事務所である。ルーブル宮と、凱旋門をうまくミックスさせ、かつ、現代的な、このグランド・アルシュの完成によって、このエトワール凱旋門からまっすぐのびる軸の両端は、ようやく完結したのであった。
12世紀のルーブル宮の建築から、800年あまり、絶対王政の「視線」を守りつつ続いてきた軸も、この軸の両端の建築物が完成したのが、1989年のフランス革命200年記念の時であるという事実を目の当たりにすると、800年かかりはしたが、やっと、壮大なる都市が実現されたような気がした。現在私達がperspectiveの視線で眺めることのできる、シャンゼリゼの「直線の美」は、時代を超えて作られた芸術とも言えるのではないだろうか・・・と私は思った。
参考文献・・・宇田英男著「誰がパリをつくったか」