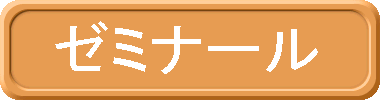
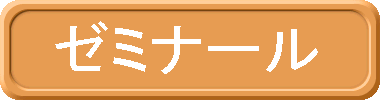
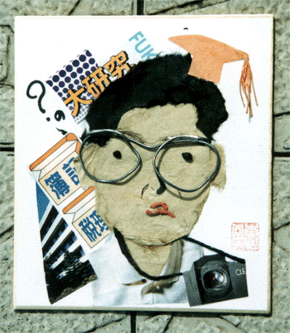
![]()
![]()
![]() ゼミナールについて考える!
ゼミナールについて考える!
![]() 土方ゼミナール
土方ゼミナール
![]() ゼミナールの風景
ゼミナールの風景
![]()
商学部では、2年後期から「演習」が開始されます。これを受講する心構えはできていますか。いまこそ真剣 |
| ◆研究のテーマ | 会計システムと情報公開のメカニズムに関する研究 |
| ◆テーマの解説 簿記・会計は、本来、企業の取引事実を帳簿に記録、計算、整理して、これを営業報告として伝達することを |
|
| ◆研究の方法 2年後期は、各自に企業を選択してもらい、営業報告を分析しながら、テキストを中心に討論を進めます。3年 |
|
| ◆要望 簿記・会計に苦手であっても興味が持てるように、その初歩から研究を進める積もりですが、ゼミナールを成果 |
|
| ◆所見 講義は黙って教師の話を聞いていれば、それで済むのですが、ゼミナールは、そうはいきません。レポーターに |
|
| ゼミは「演習」の略称。ドイツ語の"Semimar"、「実験室」を意味します。「百分は一見に如かず」ということで、 実際に自分の手で実験を行い、自分の目で確かめる、こうしたトレーニングに注目して開発されたのがゼミナー ルなのです。ただ知識を叩き込まれるのではなく、研究に没頭する教師の後ろ姿を最良の教科書として、学生 自身に研究してもらい、その環境の中から学び取らせようというわけです。自分のテーマを持ち、自分の新発見 を目指して、教師と共に研究に熱中しうる場所、自分に未知の世界が一つ一つ解き明かされていく、その面白さ を体感しうる場所、これがゼミナールなのです。 そこで、2年の後期から始まる「演習」、私のゼミですが、会社経理のメカニズムとして、簿記・会計の歴史的発 展から解き起こし、記録システム、報告システムとしての簿記・会計について学んでもらい、経理公開の問題点 としては、簿記・会計の今日的課題から解き起こし、どのような情報が引き出されうるか、どのように操作されうる か、簿記・会計の現実について学んでもらいます。実際に、好みの会社を自由に選んでもらい、会社の実績と実 状を診断しては、「ああでもない」、「こうでもない」と議論百出。とかく難解と敬遠されがちですが、この簿記・会計 に取り組むことによってこそ、会社の現実、否、日本ひいては世界の現実が見えてくるのですから。 さらに、スキンシップを高めようと、「屋外」実験室ということにして、夜の巷に出かけては、試験管よろしくビール ジョッキを片手に、酒盛りパーティの「ゼミコンパ」。はては研究ノートを旅行鞄に持ち替えて、温泉ツァーの「ゼミ 旅行」。私のゼミは実験室もかくやとばかりに、その熱気の中に和気あいあい、まさにキャンパスライフを謳歌し ています。 |