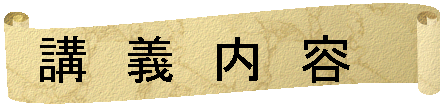
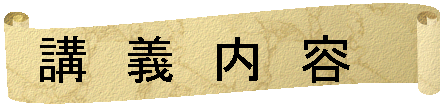
![]()
![]()
| ◆履修年次 I | ◆単位 4 |
| ◆授業時間 水1 | |
◆講義の要旨・計画 「簿記」(Bookkeeping)の語源は、「帳簿に記録する」ことである。企業および経営の活動、すなわち、取引ないし |
|
| ◆テキスト | 土方 久編著『複式簿記入門』(中央経済社)随時、プリントを配布する。 |
| ◆成績評価の方法 | 定期試験の成績(70%)に、レポート提出と出席状況(30%)を加味して評価する。 |
| ◆履修年次 II | ◆単位 4 |
| ◆授業時間 水2 | |
◆講義の要旨・内容 「会計」(Accounting)は、本来、財産ないし資本の管理と運用を委ねられた受託者が、その委託者に対して負う |
|
| ◆テキスト | 土方 久著『貸借対照表能力論』(森山書店)随時、プリントを配布する。 |
| ◆成績評価の方法 | 定期試験の成績(70%)に、レポート提出と出席状況(30%)を加味して評価する。 |
| ◆履修年次 1・1・2 | ◆単位 2 |
| ◆授業時間 月3前期・月3後期・月4前期 | |
| ◆講義の要旨・計画 「基礎演習」は、大学に「学ぶ」意義を自覚してもらい、学習の方法、自己表現の方法を修得する科目である。 |
|
| ◆テキスト | 未定 |
| ◆成績評価の方法 | 報告と質疑・討論(50%)に、レポート提出と出席状況(50%)を加味して評価する。 |
| ◆履修年次 II | ◆単位 2 |
| ◆授業時間 月4後期 | |
| ◆講義の要旨・計画 「演習I」のテーマは、会計の基本問題である「損益計算の論理」と「情報開示の論理」を研究することである。 |
|
| ◆テキスト | 土方 久著『貸借対照表能力論』(森山書店)随時、プリントを配布する。 |
| ◆成績評価の方法 | 報告と質疑・討論(50%)に、レポート提出と出席状況(50%)を加味して評価する。 |
| ◆履修年次 III | ◆単位 4 |
| ◆授業時間 水3 | |
| ◆講義の要旨・計画 「演習II」のテーマは、「演習I」のテーマと同様。 講義は、「演習I」に引き続き、「損益計算の論理」と、新たに加わる「情報開示の論理」を探求して、卒業論文を 作成するための予備工作に専念する。二三人のグループごとに「司会者」、「報告者」、「コメンテータ」の役割に 分担して、選定したテーマごとの報告をしてもらい、質疑・討論を進める予定である。また、貸借対照表および損 益計算書を実際に判読できるように、収益および費用、資産、負債および資本の意義を再検討して、今日の情 報システムとしての「会計」を修得いただければと期待している。 |
|
| ◆テキスト | 土方 久著『貸借対照表能力論』(森山書店)随時、プリントを配布する。 |
| ◆成績評価の方法 | 報告と質疑・討論(50%)に、レポート提出と出席状況(50%)を加味して評価する。 |
| ◆履修年次 IV | ◆単位 4 |
| ◆授業時間 金4 | |
| ◆講義の要旨・計画 「演習III」のテーマは、「演習I」および「演習II」のテーマと同様。 講義は、「演習II」に引き続き、「損益計算の論理」と、新たに加わる「情報開示の論理」を整理して、卒業論文 を作成するための個別指導に専念する。卒業論文のテーマごとに報告をしてもらい、質疑・討論を進める予定で ある。また、貸借対照表および損益計算書を実際に判読できるように、収益および費用、資産、負債および資本 の意義を再検討して、今日の情報システムとしての「会計」を修得いただければと期待している。 |
|
| ◆テキスト | 土方 久著『貸借対照表能力論』(森山書店)随時、プリントを配布する。 |
| ◆成績評価の方法 | 報告と質疑・討論(50%)に、レポート提出と出席状況(50%)を加味して評価する。 |