
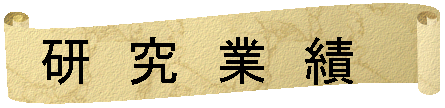


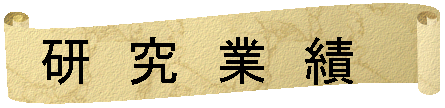

【著書】 【訳書】 【編著】 【共著】 【分担執筆】 【論文】 【資料】
『近代会計の生成−ディナミッシェ・ビランツの研究−』、 西南学院大学学術研究所 1981年4月、1-219頁. 『近代会計の基礎理論−ディナミッシェ・ビランツの研究−』、 森山書店 1981年10月、1-282頁. 『近代会計の理論展開−ディナミッシェ・ビランツの研究−』、 森山書店 1986年9月、1-207頁. 『近代会計の基礎理論−ディナミッシェ・ビランツの研究−』(増訂版)、 森山書店 1986年11月、1-344頁. 『貸借対照表能力の研究−その史的変遷と画定メカニズムについて−』、 西南学院大学学術研究所 1996年3月、1-200頁. 『貸借対照表能力論』、森山書店 1998年11月、1-313頁. 『複式簿記の歴史と論理−ドイツ簿記の16世紀−』、 森山書店 2005年12月、1-452頁. 『複式簿記会計の歴史と論理−ドイツ簿記の16世紀から複式簿記会計への進化−』、 森山書店 2008年11月、1-604頁. |
『経営維持と利潤計算』(Endres, Walter: Der erzielte und der ausschuettbare Gewinn der Betriebe, Koeln und Opladen 1967.)、 ミネルヴァ書房 1975年6月、1-247頁. |
『貸借対照表能力に関する研究』(スタディ・グループ中間報告)、 日本会計研究学会 1991年9月、1-2/39-48/55-59頁. 『貸借対照表能力に関する研究』(スタディ・グループ最終報告)、日本会計研究学会 1992年9月、1-2/29-38/70-79頁. 『貸借対照表能力論−資産および負債の定義と認識−』、税務経理協会 1993年4月、 1-3/53-64/115-128/175-188頁. 『複式簿記入門』、中央経済社 1996年4月、1-77頁. 『簿記における利益計算システムの研究』(簿記理論研究部会報告)、日本簿記学会 1996年10月、1-2/55-66/89-98頁. 『近代会計と複式簿記』(還暦記念)、税務経理協会 2003年4月、1-7/187-210頁. |
『基本商業簿記』、中央経済社 1975年6月、165-223頁. 『基本簿記原理』、中央経済社 1983年7月、1-6/174-243頁. 『新版 複式簿記入門』、中央経済社 2005年4月、1-77頁. 『新版 複式簿記入門』、中央経済社 2006年4月、1-77頁. |
『現代会計の史的研究』(関西学院大学会計学研究室編)、 森山書店 1973年11月、135-148頁. 『テキストブック会計学(2)簿記』(武田隆二編)、有斐閣 1980年4月、139-178頁. 『財務会計の論点』(武田隆二編)、同文舘 1981年6月、214-231頁. 『テキストブック会計学(2)簿記』(武田隆二編)(改訂版)、有斐閣 1983年4月、139-178頁. 『会計情報の特性に関する研究』(スタディ・グループ中間報告)、 日本会計研究学会 1989年5月、22-28頁. 『会計情報の特性に関する研究』(スタディ・グループ最終報告)、 日本会計研究学会 1990年9月、15-24頁. 『財務会計システムの研究』(興津裕康編)、税務経理協会 1999年8月、88−101頁. 『現代会計の国際的動向と展望』(津守常弘編)、九州大学出版会 1999年9月、129−141頁. 『財務諸表論がわかる』(武田隆二編)、中央経済社 2000年10月、128−137頁. 『近代会計の思潮』(岸悦三編)、同文舘 2002年9月、35-46頁. 『近代会計成立史』(平林善博編)、同文館、2005年4月、36-52頁. 『20世紀におけるわが国会計学研究の軌跡』(戸田博之・興津裕康・中野常男編)、 白桃書房、2005年11月、48-65頁. 『簿記・会計の原理−ドイツ系会計学の源流を探る−』(戸田博之・安平昭二編)、 東京経済情報出版、2005年11月、123-140頁. 『パワーアップ簿記 とことん『仕訳』』(興津裕康監修)、税務経理協会、2006年12月、11-19頁. |
「ディナミッシェ・ビランツにおける計算原則の展開」、(I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第15巻第1号、1968年6月、75-92頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第15巻第2号、1968年9月、101-119頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第15巻第3号、1968年12月、53-71頁. 「ゲルトマッハーの貸借対照表論−ディナミッシェ・ビランツとの関連において−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第16巻第2号、1969年10月、133-163頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第16巻第3号、1969年11月、87-115頁. 「ハウスナーの貸借対照表論−ディナミッシェ・ビランツとの関連において−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第17巻第2号、1970年10月、96-131頁. 「アルバッハの貸借対照表論−ディナミッシェ・ビランツとの関連において−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第18巻第3号、1971年12月、57-94頁. 「マールベルクの貸借対照表論−ディナミッシェ・ビランツとの関連において−」、 (I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第18巻第4号、1972年2月、53-89頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第19巻第1号、1972年5月、81-103頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第19巻第3号、1972年11月、253-324頁. 「ディナミッシェ・ビランツの再検討」、 『商学論集』(西南学院大学) 第21巻第3号、1974年11月、113-158頁. 「ディナミッシェ・ビランツの基底」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第22巻第3号、1975年11月、115-154頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第23巻第4号、1976年2月、121-151頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成−1673年の『フランス商業条令』について−」、 (I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第23巻第2号、1976年8月、81-117頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第23巻第3号、1976年12月、87-145頁. 「ディナミッシェ・ビランツの継承」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第24巻第2号、1977年9月、121-155頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第24巻第3号、1977年12月、119-154頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成−1861年の『ドイツ一般商法典』について−」、 (I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第25巻第3号、1978年12月、204-248頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第2号、1979年9月、56-82頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第3号、1979年12月、57-84頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成」、 『會計』(森山書店) 第116巻第5号、1979年11月、61-82頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成」、 『私学研修』(私学研修福祉会) 第84号、1980年7月、106-120頁. 「ディナミッシェ・ビランツの再吟味」、 『商学論集』(西南学院大学) 第27巻第3号、1980年12月、29-71頁. 「ディナミッシェ・ビランツにおける比較性の原則」、 『商学論集』(西南学院大学) 第27巻第4号、1981年3月、75-113頁. 「ディナミッシェ・ビランツにおける時価償却思考」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第29巻第2号、1982年10月、43-62頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第29巻第3・4号、1983年3月、459-491頁. 「ディナミッシェ・ビランツにおける恒常在高思考」、(I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第30巻第2号、1983年10月、19-42頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第31巻第1号、1984年6月、1-26頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第31巻第3号、1984年12月、55-70頁. 「ディナミッシェ・ビランツ生成前史」、 『會計』(森山書店) 第124巻第6号、1983年12月、26-44頁. 「ゲルトマッハーの力維持思考−ディナミッシェ・ビランツの継承として−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第31巻第4号、1985年3月、1-17頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第32巻第1号、1985年6月、55-84頁. 「マールベルクの中和化思考−ディナミッシェ・ビランツの継承として−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第32巻第3号、1985年12月、1-32頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第32巻第4号、1986年3月、1-23頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成契機−貸借対照表価値論争をめぐって−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第33巻第1号、1986年5月、1-27頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第33巻第2号、1986年10月、1-42頁. 「近代会計の基底を尋ねて」、 『大学時報』(日本私立大学連盟) 第37巻第198号、1988年1月、127頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成と課題−貸借対照表価値論争をめぐって−」、 『産業經理』(産業經理協会) 第47巻第4号、1988年1月、60-68頁. 「貸借対照表価値論争とディナミッシェ・ビランツ」、 『会計史学会年報』(日本会計史学会) 第6号、1988年3月、43-59頁. "The Controversy on Value in the Balance Sheet and the Dynamic Accounting Theory"、 『会計史学会年報』(日本会計史学会) 第6号、1988年3月、79-81頁. 「伝統理論における資産概念」、 『企業会計』(中央経済社) 第40巻第10号、1988年10月、28-35頁. 「貸借対照表と情報会計」、 『商学論集』(西南学院大学) 第36巻第1号、1989年6月、1-11頁. 「西ドイツの会計制度と秘密積立金」、 『産業經理』(産業經理協会) 第49巻第3号、1989年10月、43-51頁. 「情報ニーズの拡大と基準転換」、 『企業会計』(中央経済社) 第41巻第12号、1989年12月、60-66頁. 「秘密積立金と選択権」、 『商学論集』(西南学院大学) 第36巻第3・4号、1990年3月、211-237頁. 「繰延収益の負債化問題」、 『税経通信』(税務経理協会) 第45巻第12号、1990年10月、16-23頁. 「財務諸表論」、 『税経セミナー』(税務経理協会) 第36巻第15号、1991年1月、183-187頁. 「負債化能力と繰延収益」、 『商学論集』(西南学院大学) 第37巻第3・4号、1991年2月、27-42頁. 「ドイツ会計制度と貸借対照表能力」、 『産業經理』(産業經理協会) 第51巻第2号、1991年7月、23-32頁. 「貸借対照表能力の画定メカニズム」、 『商学論集』(西南学院大学) 第38巻第1・2号、1991年10月、1-20頁. 「ドイツ会計制度と貸借対照表能力の問題点」、 『會計』(森山書店) 第140巻第5号、1991年11月、81-97頁. 「固定資産の除却および売却」、 『税経セミナー』(税務経理協会) 第36巻第15号、1991年11月、148-149頁. 「個別償却と総合償却」、 『税経セミナー』(税務経理協会) 第36巻第15号、1991年11月、150-152頁. 「貸借対照表能力の問題点」、 『商学論集』(西南学院大学) 第38巻第3・4号、1992年3月、69-84頁. 「ドイツ会計制度における貸借対照表能力の帰属問題」、 『商学論集』(西南学院大学) 第39巻第1・2号、1992年9月、25-43頁. 「貸借対照表能力の帰属問題」、 『国民経済雑誌』(神戸大学) 第166巻第5号、1992年11月、21-38頁. 「静態論と貸借対照表能力」、 『商学論集』(西南学院大学) 第39巻第3・4号、1993年3月、51-82頁. 「貸借対照表能力の起点」、 『企業会計』(中央経済社) 第45巻第6号、1993年6月、126-134頁. 「動態論の構造・覚え書」、 『商学論集』(西南学院大学) 第40巻第1・2号、1993年6月、25-48頁. 「貸借対照表能力の帰属と対象」、 『會計』(森山書店) 第144巻第5号、1993年11月、46-64頁. 「動態論の貸借対照表能力」、(I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第40巻第3号、1994年1月、1-15頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第40巻第4号、1994年3月、1-16頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第41巻第1号、1994年6月、1-25頁. 「貸借対照表能力と静態論」、 『会計史学会年報』(日本会計史学会) 第12号、1994年3月、1-13頁. "Assets and Liabilities of Static Accounting"、 『会計史学会年報』(日本会計史学会) 第12号、1994年3月、81-83頁. "A Study on Definition and Recognition of Assets and Liabilities"、 "Japanese Accounting Forum" (Japan Accounting Association)、Oktober, 1994, pp.25-30. 「貸借対照表能力と選択権」、 『會計』(森山書店) 第147巻第6号、1995年6月、15-34頁 「簿記の歴史・覚え書」、 『商学論集』(西南学院大学) 第42巻第1・2号、1995年12月、35-47頁. 「貸借対照表能力の実相」、 『商学論集』(西南学院大学) 第42巻第3・4号、1996年2月、39-61頁. 「動態論と複式簿記」、 『商学論集』(西南学院大学) 第43巻第1号、1996年6月、1-13頁. 「試算表と精算表」、 『税経セミナー』(税務経理協会) 臨時増刊号、1997年3月、63-73頁. 「貸借対照表評価の価額問題−価額論争の経緯−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第44巻第1・2号、1997年12月、65-93頁. 「貸借対照表評価の選択権問題−秘密積立金政策の転換−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第44巻第3・4号、1998年2月、43-72頁. 「貸借対照表評価の価額問題−価額論争の終息−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第45巻第1号、1998年6月、1-32頁. 「選択権と貸借対照表能力」、 『商学論叢』(福岡大学) 第43巻第4号、1999年3月、957-986頁. 「静態論の財産計算」、 『商学論集』(西南学院大学) 第46巻第3・4号、2000年1月、21-32頁. 「シュマーレンバッハの動的貸借対照表論」、 『経済学論集』(神戸学院大学) 第31巻第4号、2000年3月、17-34頁. 「動態論の損益計算」、 『商学論集』(西南学院大学) 第47巻第1号、2000年6月、1-17頁. 「簿記の構造・覚え書」、 『商学論集』(西南学院大学) 第47巻第2号、2000年10月、1-22頁. 「ドイツ固有の簿記の成立−Grammateus, Henricus 1518年−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第48巻第2号、2001年10月、1-30頁. 「ドイツ固有の簿記の展開−Gottlib, Johann 1531年−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第48巻第3・4号、2002年2月、23-52頁. 「ドイツ固有の簿記の展開−von Ellenbogen Erhart 1537年−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第49巻第1号、2002年6月、91-120頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第49巻第2号、2002年9月、51-70頁. 「ドイツ固有の簿記の発展−Gottlib, Johann 1546年−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第49巻第1号、2002年6月、1-38頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第49巻第2号、2002年9月、1-32頁. 「ドイツ固有の簿記の残影−Kaltenbrunner,Jacob 1565年−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第50巻第1・2号、2003年9月、1-29頁. 「ドイツ簿記の16世紀−印刷本の年表と目録−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第50巻第1・2号、2003年9月、109-138頁. 「16世紀前半におけるドイツ固有の簿記」、 『松山大学論集』(松山大学) 第15巻第2号、2003年6月、57-82頁. 「ドイツ簿記とイタリア簿記の交渉−Schweicker, Wolffgang 1549年−」、(I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第50巻第3号、2003年12月、1-22頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第50巻第4号、2004年3月、1-36頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第51巻第1号、2004年7月、1-59頁. 「16世紀における複式簿記の風景」、 『商学論集』(西南学院大学) 第51巻第1号、2004年7月、137-171頁. 「複式簿記の歴史と構造」、 『経済論叢』(近畿大学) 第2巻第1号、2004年4月、1-11頁. 「イタリア簿記の原型−Pacioli, Luca 1494年−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第51巻第2号、2004年9月、1-45頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第51巻第3・4号、2004年2月、1-34頁. 「ドイツにおけるイタリア簿記の発展−Goessens, Passchier 1594年−」、(I)、(II)、(III) 『商学論集』(西南学院大学) 第52巻第1号、2005年6月、1-25頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第52巻第2号、2005年9月、1-41頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第52巻第3号、2005年12月、1-48頁. 「ドイツにおけるイタリア簿記の展開−Sartorium, Wolffgangum 1592年−」、(I)、(II)、(III) 『商学論集』(西南学院大学) 第52巻第4号、2006年3月、1-28頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第53巻第1号、2006年6月、1-23頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第53巻第2号、2006年9月、1-38頁. 「ドイツにおけるイタリア簿記の再生−Gamersfelder, Sebastian 1570年−」、(I)、(II)、(III) 『商学論集』(西南学院大学) 第53巻第3.4号、2007年2月、25-79頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第1号、2007年6月、27-79頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第2号、2007年9月、49-106頁. 「複式簿記会計への進化−17世紀から19世紀までの単式簿記と複式簿記−」、(I)、(II)、(III) 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第3号、2007年12月、1-42頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第4号、2008年2月、1-43頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第55巻第1号、2008年6月、1-58頁. 「冒険貸借と徴利禁止令−大航海時代における複式簿記からの疑問−」、(I)、(II)、(III) 『商学論叢』(近畿大学) 第54巻第1号、2008年7月、9-19頁. 「冒険貸借と徴利禁止令−大航海時代における複式簿記からの疑問−」、 『会計史』(日本会計史学会) 第27号、2009年3月、13-27頁. 「記録の起源と複式簿記の記録」、(I)、(II)、(III)、 『商学論集』(西南学院大学) 第56巻第3・4号、2010年3月、31-48頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第57巻第1号、2010年月、1-27頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第57巻第3号、2010年月、1-28頁. 「ドイツ固有の簿記の再考−von Ellenbogen, Erhart 1538年−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第57巻第4号、2010年月、1-45頁. 「ドイツ固有の簿記の再説−von Ellenbogen, Erhart 1537年−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第57巻第4号、2011年3月、1-39頁. |
「架空利潤の計算−ベンダーの見解について−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第18巻第1号、1971年6月、95-109頁. 「稼得利潤と処分可能利潤−エントレスの見解について−」、(I)、(II)、(補)、 (III)、(IV)、(V)、 『商学論集』(西南学院大学) 第20巻第1号、1973年6月、123-167頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第20巻第2号、1973年8月、117-153頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第20巻第3号、1973年11月、243-283頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第20巻第4号、1974年2月、195-228頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第21巻第1号、1974年5月、295-345頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第21巻第2号、1974年8月、83-130頁. 「ディナミッシェ・ビランツの研究−損益計算における貨幣価値調整−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第21巻第4号、1975年2月、197-221頁. 「ディナミッシェ・ビランツの研究−貨幣価値調整についての例示−」 『商学論集』(西南学院大学) 第23巻第4号、1977年2月、79-104頁. 「ワルプの貸借対照表学説史−ドイツ高等商事裁判所の判決からシェフラーの貸借対照表論まで−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第25巻第1号、1978年6月、49-77頁. 「ディナミッシェ・ビランツの研究−貸借対照表法規の展開について−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第25巻第2号、1978年9月、53-84頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第25巻第3号、1978年12月、361-389頁. 「ディナミッシェ・ビランツの生成−貸借対照表法規と判決について−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第1号、1979年6月、185-204頁. 「シュマーレンバッハの文献目録」、 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第2号、1979年9月、83-123頁. 「カメラル会計の構造−行政カメラル学について−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第3号、1979年12月、85-122頁. 「カメラル会計の構造−経営カメラル学について−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第26巻第4号、1980年3月、81-119頁. 「カメラル会計の展開−ワルプの見解について−」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第27巻第1号、1980年6月、59-79頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第27巻第2号、1980年10月、79-98頁. 「ドイツ貸借対照表法史の研究」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第28巻第4号、1982年3月、67-90頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第29巻第1号、1982年8月、49-74頁. 「ディナミッシェ・ビランツの新展開−シェミレヴィッチのFBEシステム論について−」、 (I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第29巻第2号、1982年10月、63-105頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第30巻第1号、1983年6月、49-85頁. 「ディナミッシェ・ビランツと正規の簿記の諸原則」、 『商学論集』(西南学院大学) 第30巻第2号、1983年10月、97-116頁. 「正規の簿記の諸原則について−ディナミッシェ・ビランツの理解のために−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第31巻第2号、1984年11月、123-163頁. 「ディナミッシェ・ビランツの研究−貸借対照表価値論争の出発点について−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第33巻第1号、1986年5月、73-86頁. 「『ディナミッシェ・ビランツ』−文献解題」、 『商学論集』(西南学院大学) 第33巻第3号、1986年12月、81-106頁. 「ドイツ税法会計史の研究−バルト著『貸借対照表法の発展』をめぐって−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第34巻第3号、1987年11月、153-175頁. 「秘密準備金の分類」、 『商学論集』(西南学院大学) 第35巻第4号、1989年3月、161-183頁. 「ドイツ商法における貸借対照表能力」、 『商学論集』(西南学院大学) 第37巻第3・4号、1991年2月、181-211頁. 「貸借対照表能力と経済財」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第38巻第1・2号、1991年10月、51-83頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第38巻第3・4号、1992年3月、197-212頁. 「スタディ・グループ報告要旨『貸借対照表能力に関する研究』(中間報告)」、 『企業会計』(中央経済社) 第43巻第12号、1991年12月、88頁. 「スタディ・グループ報告『貸借対照表能力に関する研究』(中間報告)」、 『日本会計研究学会会報』(日本会計研究学会) 1992年4月、19-20頁. 「ドイツ税法と資産化能力のある経済財」、 『商学論集』(西南学院大学) 第39巻第1・2号、1992年9月、153-184頁. 「スタディ・グループ報告要旨『貸借対照表能力に関する研究』(最終報告)」、 『企業会計』(中央経済社)第44巻第12号、1992年12月、87-89頁. 「スタディ・グループ報告『貸借対照表能力に関する研究』(最終報告)」、 『日本会計研究学会会報』(日本会計研究学会) 1993年4月、16-18頁. 「簿記理論研究部会報告『簿記における利益計算システムの研究』(中間報告)」、 『日本簿記学会年報』(日本簿記学会) 第11号、1996年10月、99-104頁. 「会計制度における『選択権』の行使と、これに伴う秘密積立金政策の転換に関する研究」、 『Seinan Ricerca』(西南学院大学学術研究所) 第1号、1996年10月、16-17頁. 「1985年のドイツ商法と貸借対照表能力」、 『商学論集』(西南学院大学) 第43巻第2号、1996年9月、83-107頁. 「簿記理論研究部会報告『簿記における利益計算システムの研究』(最終報告)」、 『日本簿記学会年報』(日本簿記学会) 第12号、1997年10月、7-13頁. 「複式簿記の発達と、その背景にある中世ドイツ都市史および商業史に関する実例研究」、 『Seinan Ricerca』(西南学院大学学術研究所)第10号、2006年2月、4-5頁. 「16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録」、 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第3号、2007年12月、169-196頁. 「複式簿記会計の歴史と論理−ドイツ簿記の16世紀から複式簿記会計への進化−」、 『商学論集』(西南学院大学) 第55巻第1号、2008年6月、187-205頁. 「大航海時代の到来によって変化する交易形態の実状と、16世紀・商業帳簿の記録の研究」、 『Seinan Ricerca』(西南学院大学学術研究所) 第13号、2009年2月、1-3頁. 「19世紀のドイツに出版される簿記の印刷本の目録」、(I)、(II)、 『商学論集』(西南学院大学) 第57巻第2号、2010年9月、73-100頁. 『商学論集』(西南学院大学) 第54巻第3号、2010年月、161-193頁. |
「ウォルター・エンドレス著『経営の稼得利潤と処分可能利潤』」、『企業会計』(中央経済社) 第26巻第1号、1974年1月、182-183頁. 「五十嵐邦正著『静的貸借対照表論の展開』」、『會計』(森山書店) 第144巻第5号、1993年11月、141-144頁. |
『会計学辞典』(第4版)(神戸大学会計学研究室編)、同文舘1976年10月、158-159/321-322/1093頁. (「カメラル簿記」、「ゲルトマッハーの会計学説」、「マールベルクの会計学説」) 『現代簿記会計用語辞典』(宇南山英夫・安平昭二編)、 同文舘 1983年11月、22-23/39-40/62/85-86/91-92/93/135/171/178-179/179/195-196/236-237/258/260/ 263-264/293-294/330-331/375-376/393頁. (「運動貸借対照表」、「会計史学」、「貨幣資本維持説」、「期末棚卸制度」、「金融経済的貸借対照表」、 口別損益計算」、「購買力資本維持説」、「資金動態論」、「実質資本維持説」、「実体資本維持説」、 「収支的貸借対照表論」、「静態論」、「貸借対照表制度」、「貸借対照表論」、「多元評価」、「動態論」、 「費用動態論」、「名目資本維持説」、「リトルトン」) 『会計学大辞典』(第4版)(森田哲彌・岡本清・中村忠編)、中央経済社1996年9月、 15-16/488/609-610/688/698-699/701/792頁.(「移管品」、「自製材(原)料」、「正規の簿記の原則」、 「貸借対照表能力」、「棚卸資産」、「棚卸資産原価」、「投資」) 『会計学辞典』(第5版)(神戸大学会計学研究室編)、同文舘1997年6月、 182-183/277-278/364-365/437/596/651-652/665/739/819/835-836/931/1047-1048/1146-1147頁. (「カメラール簿記」、「基礎有高法」、「ゲルトマッハー」、「拘束有高」、「支出」、「収益」、 「収入」、「成果」、「損益」、「貸借対照表能力」、「投機有高」、「費用」、「マールベルク」) 『現代会計用語辞典』(興津裕康・大矢知浩司編)、税務経理協会 1999年12月、 3/90/90-91/169-170/185-186/224頁. (「後給付」、「財産法」、「財産目録」、「中和化」、「動的貸借対照表」、「前給付」) 『現代簿記会計用語辞典』(第2版)(宇南山英夫・安平昭二編)、 同文舘 2001年4月、18-19/52/73-74/79/81/118/150/157-158/158/172-173/177-178/208/228/229/233/259/ 291-292/329/343-344頁. (「運動貸借対照表」、「貨幣資本維持説」、「期末棚卸制度」、「金融経済的貸借対照表」、 「口別損益計算」、「購買力資本維持説」、「資金動態論」、「実質資本維持説」、「実体資本維持説」、 「収支的貸借対照表論」、「シュマーレンバッハ」、「静態論」、「貸借対照表制度」、「貸借対照表論」、 「多元評価」、「動態論」、「費用動態論」、「名目資本維持説」、「リトルトン」) 『現代会計用語辞典』(第2版)(興津裕康・大矢知浩司編)、 税務経理協会 2002年4月、3/98/98-99/180/196-197/237頁. (「後給付」、「財産法」、「財産目録」、「中和化」、「動的貸借対照表」、「前給付」) 『現代会計用語辞典』(第3版)(興津裕康・大矢知浩司編)、 税務経理協会 2005年5月、3/102/102/187/203-204/242/245頁. (「後給付」、「財産法」、「財産目録」、「中和化」、「動的貸借対照表」、「保守主義の原則」、 「前給付」) 『会計学大辞典』(第5版)(安藤英樹・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編)、 中央経済社 2007年5月、21/634/793-794/893-894/913/1027-1028頁. (「移管品」、「自製材(原)料」、「正規の簿記の原則」、「貸借対照表能力」、「棚卸資産」、 「棚卸資産原価」、「投資」) 『会計学辞典』(第6版)(神戸大学会計学研究室編)、 同文舘 2007年11月、25-26/274-275/358/432/577-578/578-579/582-583/628-629/643/651-652/714/784-785/ 799-800/901/1001-1002/1013-1014/1018-1019/1032-1033/1110-1111頁. (「一致の原則」、「基礎有高法」、「ゲルトマッハー」、「拘束有高」、「資産」、「資産の現金性」、 「支出」、「シュヴァイカー」、「収益」、「収入」、「シュマーレンバッハ」、「成果」、「損益」、 「貸借対照表能力」、「投機有高」、「比較性の原則」、「費用」、「評価論の発展」、「フィッシャー」、 「マールベルク」) |
【学会報告】(学研報告書で要調査)
多数のために省略.
『1861年のドイツ商法における財産目録と貸借対照表の研究』、「科学研究費補助金・一般研究C」、 1978年. 『ドイツ株式法における財産目録と貸借対照表の研究』、「科学研究費補助金・一般研究(C)」、 1979年. 『ドイツ商法および税法の変遷に伴う、貸借対照表に関する評価規定の研究』、 「科学研究費補助金・一般研究(C)」、1984年. 『ドイツ貸借対照表価値・計上論争の経緯と株式会社会計の変貌に関する研究』、 「科学研究費補助金・一般研究(C)」、1987年. 『貸借対照表計上能力の史的変遷と、その画定メカニズムに関する研究』、 「科学研究費補助金・一般研究(C)」、1992年. 『会計制度における『選択権』の行使と、これに伴う秘密積立金政策の転換に関する研究』、
「西南学院大学・特別研究(C)」、1994-95 |