|
|
 |
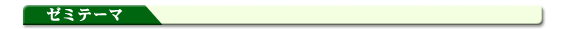 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
文化人類学から世界を見ることを試みます。文化人類学では、自分自身や自分が生まれ育った社会では当然とされるものを、いったん括弧に入れて思考します。ゼミで「貧困問題について考えたい」という人には、「貧しい」とは何かを問いかけます。「アフリカ人女性の社会進出について知りたい」という人には、「社会進出」とは何かを問いかけます。答えにつまったら、考えて調べて、また考えればいいのです。
ゼミでは皆さん自身が何をどう知りたいのかが問われます。自分が何を知りたいのかを知るため、本、映画、日常生活、そして多様な授業を通じて、物事を多角的に批評的に思考する視座を養ってください。 |
|
 |
|
|
 |
| 1年次で「文化コース基礎論」を受講して、文化や社会を比較の視点から見るとはどういうことか、学び考えてください。2年次以降に履修できる「文化人類学」や「文化社会学」では、歴史的・共時的な視座から社会や文化について考えいきますので、ぜひ参加してください。また、社会のいろいろな事象について興味はあるけれど、それをどのように調べればいいのかつかめない人は、「社会調査法」や「社会調査実習」でその一端を学ぶことができます。 |
|
 |
|
|
 |
| 北九州市小倉と福岡市で育ちました。大学周辺の西新や百道は、小学校の頃からうろついていた地元です。大人になってからは、足掛け15年間京都に暮らしました。そのあいだにおよそ2年間、西アフリカのマリで過ごしました。西アフリカには、今でもたびたび渡航しています。キャンプや畑での野菜作りが最近の趣味です。こう書くと友人が多くアクティブに思われますが、友人は心からそう思える人が一生に2,3人いれば十分に豊かだと思っています。 |
  |
|
 |
|
|
 |
■平野千果子
『アフリカを活用する: フランス植民地からみた第一次世界大戦』(人文書院、2014年)
戦争はいけません、植民地支配はいけませんと言うのは簡単です。なぜ私たちはそんな「いけないこと」を繰り返してきたのかは、過去に学ぶしかありません。
■小川さやか
『都市を生きぬくための狡知ーータンザニアの零細商人マチンガの民族誌』(世界思想社、2011年)
一見混沌としているように見えるタンザニアのストリート、実際はどうなのでしょうか。内側から追体験してみてください。
■A.V.バナジー&E.デュフロ
『貧乏人の経済学ーーもういちど貧困問題を根っこから考える』(みすず書房、2012年)
「世界の貧困問題を解決したいです!」と息巻く人に、良い意味で出鼻をくじかれるといいなと思っておすすめしている本です。くじかれてからが勝負です。
■ハンナ・アーレント
『エルサレムのアイヒマンーー悪の陳腐さについての報告』(新版)(みすず書房、2017年)
思考しないことがいかに罪なのかを、思考し続けた人間が指摘しています。
■オルテガ・イ・ガセット
『大衆の反逆』(岩波新書、2020年)
ここでいう「大衆の反逆」は、「下々の者よ、みんなで立ち上がろう!」という意味ではありません。どういう意味なのかは、読んでからのお楽しみ。辛辣な本です。
■松村圭一郎
『これからの大学』(春秋社、2019年)
大学での学びだけでなく、生きるということ・学ぶということについて考えるよいきっかけになると思います。松村さんの『うしろめたさの人類学』もおすすめです。
■チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
『アメリカにいる、きみ』(河出書房新社、2007年)
ナイジェリア出身の作家アディーチェの短編集です。どこか冷めつつも瑞々しい感性があふれています。アフリカ出身者の小説を読んだことがない人に。
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |