|
|
 |
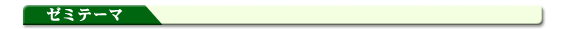 |
 |
| 現代世界を哲学する |
 |
|
|
 |
|
|
 |
今日、私たちが生きている世界とは、いったいどのようなものなのでしょうか。そこで私たちは、いったいどのように生きていくことを余儀なくされているのでしょうか。そしてまた、それとは別の仕方で生きることが、いったいどのようにして可能なのでしょうか。このゼミでは、そうした一連の問いに導かれながら、現代世界の状況に迫っていきます。
現代世界は、グローバル化の時代にあると言われます。そこでは、国際文化が多様性を称揚しながらも、著しく均質化しているという逆説的な事態が見られます。このゼミではそれゆえ、世界各地の文化状況を比較検討することによって、それらに共通して見られるグローバリズムの諸問題を探っていきます。たとえば、経済格差の拡大、対テロ戦争、サイバー監視社会、気候変動といったような問題です。そしてまた、そうした諸問題を批判的に分析するために、現代哲学や現代思想の重要著作をひもといていきます。
|
|
 |
|
|
 |
現代哲学や現代思想は、とりわけ西欧で発展してきたので、第二外国語としては、フランス語ないしドイツ語を履修することを強くお勧めします。
また、1〜2年次には、共通科目の「哲学」と「倫理学」を履修してください。専攻科目の「文化コース基礎論e」(比較文化コース)も受講してもらえたらと思います。2〜3年次には、専攻科目の「現代思想文化論」を履修してください。
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| 1980年、神奈川県生まれです。フランスのパリ東大学大学院人文科学研究科を修了し、哲学の博士号を取得しました。専門は現代哲学で、とりわけミシェル・フーコーというフランスの思想家を研究しています。好きなことは旅行です。 |
|
 |
|
|
 |
現代思想は概して、私たちが長らく安らってきた近代社会への批判を通じて発展してきました。その批判に先鞭をつけたのが、一九世紀ドイツの思想家ニーチェです。そして、その企てを極限まで推し進めようとしたのが、二〇世紀ドイツの哲学者ハイデガーであり、さらにはまたフランスの思想家フーコーです。ここでは、彼らの主著を取り上げ、その思想的系譜へとご案内します。
■ニーチェ『ツァラトゥストラはこう語った』(1883〜1885年)
もし神が存在しないとすれば、生きる意味はいったいどこにあるのでしょうか。私たちはいったい何のために生きていけばよいのでしょうか。本書は、近代世界の「神の死」以降、そのニヒリズムを克服するために執筆された本です。入門書として、三島憲一『ニーチェ』(岩波新書、1987年)から始めることをお勧めします。
■ハイデガー『存在と時間』(1927年)
世間のひとは、この日常があたかも永遠に続くかのように毎日を何となく過ごしています。しかし死はいずれ必ずやってきます。死と向きあって、おのれ本来の生を生きなくてはならないのです。本書は、その決断を私たちに強く迫る本です。木田元『ハイデガーの思想』(岩波新書、1993年)から入門することをお勧めします。
■フーコー『言葉と物』(1966年)
今日、ひとは皆、人間であることに安住しています。しかし人間とは実のところ、乗り越えられるべき存在であって、今後、私たちはおのれ自身で、新たな生を創造していかなくてはならないのです。本書は、その来るべき「人間の死」を告知した本です。概説書として、慎改康之『ミシェル・フーコー』(岩波新書、2019年)をお勧めします。
大学時代、二〇歳前後の頃は、自分自身を確立する時期なので、精神的な試練も少なからずあるだろうと思います。それはまさに一人旅に出るようなものです。本はそのとき、貴重な伴侶になってくれます。読書とともに、そうした日々を過ごしてもらえたらと思います。「僕は二〇歳だった。それが人生の中で最も美しい時期だなんて誰にも言わせまい」(ポール・ニザン『アデン アラビア』)。
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |